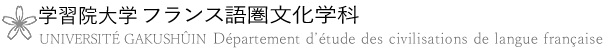■研究テーマ: 映画批評、フランス映画史
■略歴・主要業績
■研究領域
私の専攻は映画批評で、ヌーヴェル・ヴァーグという1950年代末にフランスで興った映画運動に主に関心を寄せてきました。パリ第三大学に提出した博士論文では、「究極のヌーヴェル・ヴァーグ」とか「ヌーヴェル・ヴァーグの真の後継者」などと語られてきたジャン・ユスターシュを取り上げ、彼の監督作の生成過程を辿り直しました。アーカイヴ資料を調査し、企画書やシナリオ草稿などを丹念に分析するとともに、各作品の制作に関わったスタッフや知人ら多くの人物に聞き取り調査をすることで、ユスターシュがどのような着想のもとに企画を立ち上げ、映画として仕上げていったかを描き出そうとしました。『評伝ジャン・ユスターシュ』はそれを日本語に書き改めたものです。
フランスに留学して博士論文を執筆するという、これほどまでに映画に興味を持ったきっかけは、いま思うと1本の映画でした。ジャン゠リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』を見たのがそもそものはじまりだと思います。この映画に出会わなければ、フランス語の勉強を始めることもなかったはずです。初めて覚えたフランス語の表現は、劇中でジーン・セバーグがたびたび口にする「Qu'est-ce que c'est ?」でした。
アメリカ合衆国出身の学生で、新聞社でインターンをしているパトリシア。彼女は知らない単語を聞くたびに、「Qu'est-ce que c'est ?(それは何ですか?)」と質問します。言葉の意味がそのつど確かめられ、そしてすべてが定義し直されていきます。最後にもう一度同じ質問を呟く彼女を正面から捉えるラストは、あたかもこの問いそのものを観客に受け渡すかのようです。『勝手にしやがれ』は「Qu'est-ce que c'est ?」の問いのもとにすべてを再審に付し、それまでの映画のあり方をひっくり返してしまう。この作品を見た誰もが「これは何だ?」と疑問を抱き、しまいには「映画とは何か?」と自問自答せずにいられなくなるとすれば、それは幾度も繰り返される主人公の疑問文に触発されてのことです。
私はゴダールの映画を通してフランス語の表現を知っただけでなく、何に対しても「これは何?」「あれは何?」と疑問を抱く好奇心そのものを芽生えさせられたような気がします。それはいまだに衰えることがありません。わからないものに出会っては何にでも好奇心を抱く。そんな生活をずっと続けています。
■私の授業
ゼミナールでは、フランス語で書かれた雑誌や新聞の文化欄の記事を読み、現在の文化動向に触れてみたいと思っています。最近の事象を知ることは、これまでに積み重ねられてきた歴史を学ぶことに繋がります。映画を中心に、芸術・文化・社会に関わるさまざまな領域を扱う予定です。
語彙や構文を吟味しながら文意を読み取っていく精読の練習を繰り返すことで、初読でも素早く大意を捉え、おおよその趣旨を理解する能力を身につけることを目指します。また、文章を読むときに大事になのは、体に言葉のリズムを馴染ませること。フランス語のリズムに慣れ親しむために、映画やテレビやラジオのような視聴覚メディアを必要に応じて活用していきたいと思います。